
参照: 環境省『ペット動物販売業者用説明マニュアル』「動物の特性と飼養方法」 より
哺乳類の飼育について -飼い方のポイントと注意点-
ウサギ・ハムスター・モルモットについてのご紹介です。その他の哺乳類につきましては、下記PDFをご参照下さい。
ウサギ
(1) 繁殖制限
繁殖を希望しない場合は1頭飼いが原則です。オスのほうが人なつっこい傾向がありますが、性成熟を迎える前の生後4~6ヵ月頃(品種により違いがあります)に去勢手術をすればスプレー行動などがなくなることが多く、発情時の気の荒さもなくなり非常に飼いやすくなります。1つのケージでのオスどうしの複数飼いはけんかをするので避けましょう。メスどうしの複数飼いは可能ですが、その場合にも性成熟を迎える前に不妊手術をしたほうが発情のストレスもなくなりウサギのためにはよいでしょう。
(2) 食 事
主食は専用のペレット(固形飼料)と乾牧草にし、おやつ程度に小松菜などの根菜類・菜っ葉類、りんごなどの果物、オオバコなどの野草を与えます。また、ミネラル補給のための塩土と、歯の伸びすぎ防止のための「かじり木」は常置しておきます。湿気に弱いといっても水は大変よく飲みますので、常に新鮮な水を用意しましょう。なお、下痢をしやすいので水分の多い野菜や果物の多給は控えることが大切です。ペレットは1日に朝夕の2回、30分程度で食べきってしまう程度の量を与えます。乾牧草はいつでも食べられるように新鮮なものを入れておきます。嗜好性にかたよりがみられることが多いので、若いときからペレットと乾牧草に十分に馴らしておくことが重要です。
(3)食物の注意点
野菜や果物は、農薬やワックスなどの危険があるのでよく洗い、下痢を防ぐために水気が乾いてから与えるようにします。また、野草を与える場合は、除草剤がかかっていると致命的ですので要注意です。与えてはいけないものに、肉類や、タマネギ、ニラ、ニンニクなどの刺激性のある野菜類、チョコレート、クッキー、ケーキなどの甘いものや人間の食べ物、有毒な園芸植物、観葉植物、野草があります。
なお、干牧草はダニやカビの発生を防止するため、買って帰ったらいったん天日干ししてから湿気ないように密封して保管するのが適切です。これは、寝床や床材として使用する場合も同様で、ワラにも同じことがいえます(以下、小型哺乳類はこの項については同様)。
(4) 収容物等の手入れ
尿の量が大変多いので、トイレや寝床の汚れた部分、すのこの下の新聞紙はこまめに取り替え、食事の管理ごとに食器や給水ビンもよく洗い、適宜すのこもよく洗って乾燥させ、週に1回か高温多湿の時期はそれ以上にケージ全体を洗剤で洗うか熱湯消毒して天日干しをします。
(5) その他の手入れ、しつけ
幼齢時からブラッシングに馴らし、時々心掛けましょう。特に毛が抜け替わる春から夏にかけては念入りにする必要があります。湿気に弱いのでシャンプーは禁物です。爪が伸びすぎると歩行困難を起こしますので、伸びた場合には爪切りが必要です。
トイレのしつけは犬の場合と同じようにできますので、ぜひ覚えさせましょう。覚えやすいように、最初にトイレの中に自分の排泄物の臭いがついたものを少し入れておくのがコツです。
(6) 運 動
ケージの中だけでは運動量が足りません。目の届くときに部屋の中で遊ばせましょう。その際、室内にはケガや事故の原因となるものが多いことに留意し、予め防止策を講じておくことが必要であり、これは他の動物の場合も同じです(電気コードや観葉植物、家具類、たばこなどかじられたり食べられたりしないように、また、家具類の上の置物が落下しないようにします)。床が畳だとかじられますし、板だと滑りやすいので、床には爪が引っ掛からないじゅうたんを敷きます。合成繊維のカーペットは齧って飲み込んだときに固い毛玉になって胃にたまりますし、ループ状のカーペットは爪を引っかけて骨折の原因になるので避けましょう。遊ぶときに、敏感な耳を掴んで持ち上げるのは苦痛となるので禁物です。また、後肢を支えて抱くのは、時にジャンプして落下したときに骨折しやすいので、これも禁物で、抱くときは必ずお尻を支えにしましょう。
(7) 逸走防止等
ケージに入れている間は、逸走防止のためケージの扉はナスカンなどでしっかりと留めて置きましょう。逸走防止のため、室内に放すときはもちろん、日常の掃除、ケアー時にも窓やドアはきちんと閉めてあるかどうか確認することが大切です。
(8) 危害防止、迷惑防止
門歯に指を引っかけてケガをする場合も多いので、特に幼児がケージの間から指を入れないよう、また室内で一緒に遊んでいる際にも不用意に口許に指を近づけないよう注意することが必要です。
屋外施設で飼っている場合には、糞尿の臭いや衛生害虫の発生、コクシジウム感染防止のため、こまめに掃除を心掛け、周囲への迷惑防止を図らなければなりません。
ハムスター
<環境など>
ドワーフ及びチャイニーズ以外の単独性のハムスターはつがいにせず1頭ずつ別々の収容物で飼うのが原則です。縄張り意識が強く、オス・メスどうしでもけんかしてしまうからです。もし繁殖を希望するならオス・メスの見合い期間を設けて相性を見るなどの措置が必要ですが、生まれた子供の数だけ収容物が必要となりますので、覚悟が必要です。繁殖を希望しないなら、1年中繁殖が可能で性周期も短いためすぐに増えてしまいますので、オス・メスを一緒に飼うのは禁物です。
晩秋頃から冬季にかけてはヒマワリの種やクルミを多めに与えて体力をつけ、保温に気をつけて、飼養下では冬眠させないで飼ったほうが無難です。
<食事など>
主食は専用のペレットにし、副食として色々なものを少しずつ与えましょう。1日に1回、夕方の活発に動き回る頃にエサを与え、傷みやすい副食の食べ残しはしばらくして片づけましょう。ハムスターは下痢を起こしやすく、下痢をしたら致命的になりやすいからです。ま
た、傷んだエサは頬袋の炎症の原因にもなります。
副食としては、根菜類や野菜、ハト用配合飼料などの穀類、アルファルファなどの乾牧草があります。大好物のヒマワリの種やクルミ、ピーナッツなどの種子類は脂肪分が多いのでおやつ程度に、ふれあいを図るために与え、肥り過ぎに注意します。
また、一日おきくらいにペット用煮干しやゆで卵の白身などの動物性食品やリンゴなどの果物を与えます。なお、ミネラル補給のための塩土と、歯の伸びすぎを防ぐため「かじり木」は常時置いておきます(これは、以下のげっ歯類に共通します)。毎日、巣の中に溜め込んだ食物を点検し、生ものや腐りそうな物は取り除きます(巣の中に食物を貯める習性のあるものは、以下同様にします)。
<トイレ・手入れ>
ケージ等や個体の手入れ、しつけはウサギに準じます。なお、トイレ砂は全部を取り替えますが、臭いの付いたものを少しだけ残しておきます。同様に、週に1回は床材と巣材を全部取り替えますが、臭腺で縄張りに臭い付けしていますので、汚れていない古い床材を少し混ぜます。
<接し方>
夕方などに一緒に遊んでやれば運動にもなりますし、よく馴れます。おやつを使って人の手によく馴らしましょう。また、自由にしておくならともかく、長時間手でいじることはハムスターにとっては大きなストレスになり健康を害することになるということに留意しなければなりません。
逸走防止はウサギに準じます。ハムスターの背後又は上方から急に掴もうと手を出したり、眠っている時や仰向けになって「キーキー」と声を出している時(これは怒っているか、怯えている時のしぐさ)やよくなついていないものにうっかり手を出すと咬まれることがあり、意外に深い傷を受けることがありますので、幼児などが不用意にケージの中に指を入れないよう注意する必要があります。
モルモット
<環境など>
居性なので複数飼いは可能ですが、オスどうしは順位づけのためにけんかし、逃げ場所がないとケガをしますし、オス・メス混合飼養だとすぐに繁殖してしまいますので、考慮が必要です。
<食事など>
主食はビタミンC入りのモルモット専用ペレットにし、毎日朝夕2回与えます。ビタミンCは空気にふれると壊れやすいので、消費期限に注意し、開封したら保管に注意が必要です。副食としてビタミンCの豊富な色々な野菜(レタスは適しません)や、タンパク質が豊富な乾牧草(アルファルファなどのマメ科のものが適切。モルモットは植物性タンパク質を多く必要とし、また歯の伸びすぎ防止にもなります。)を毎日少しずつ与えます。ハコベやナズナ、シロツメグサ、タンポポなどの野草も喜びます。ビタミンCの豊富なミカンやイチゴ、キウイ、リンゴなどの果物も、糖分が多いので与えすぎに注意しながら時々与えましょう。カルシウム補給のためにペット用煮干しも時々与えます。
<トイレ・手入れ>
トイレのしつけは基本的にはできないと考えたほうがよく、また排泄物の量が多いので、床材の汚れた部分は毎日取り替え、すのこの下の新聞紙も湿気予防のために濡れたら上から取り除いていくと手間がかかりません。
長毛種は糞がこびりつきやすいので、お尻の部分の毛はカットするなりして、ストレスを感じさせないように注意しながら時々ブラッシングも心がけましょう。
<接し方>
淋しがり屋なので1日1回はケージから出して遊ばせることが大切ですが、大声を出したり、急に乱暴に抱き上げて驚かせるとショック死することもありますので気を付けましょう。機嫌が悪い時に「キー、キー」と鳴いたり歯をガチガチと鳴らしたりすることがあります。
飼育について、より詳細な情報をお求めの方
より詳細な情報をご覧になりたい方は、下記のPDFファイルをご参照下さい。
※上記の記載は、下記PDFファイルの抜粋になります。
環境省 『ペット動物販売業者用説明マニュアル』「動物の特性と飼養方法」 より
|

哺乳類・ 鳥類・ 爬虫類 |
pdfファイルをご覧になるには、adobeリーダーが必要です。
adobeリーダーのダウンロードはこちらから→ |
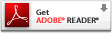 |
|



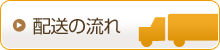
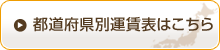
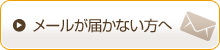

![TEL 0266-44-3952([平日] 15:00~19:30 [土曜日及び日祭日] 13:00~20:00 定休日無し ※臨時休業有り) FAX 0265-79-7977](/user_data/packages/kittou/images/base/banner_mail.gif)
