
参照: 環境省『ペット動物販売業者用説明マニュアル』「動物の特性と飼養方法」 より
爬虫類の飼育について -適正飼養を確保するために必要な情報-
爬虫類には多くの種が含まれており、それぞれの種によって要求する飼育環境や管理が異なります。正確な情報のもとに、飼育環境の設定、管理が行われ、適正な飼育が行われるようにしなければなりません。
以下に、一般的に留意すべき点について大まかに述べることとしますが、常に動物の状態を観察して、最初の環境設定や管理方法を修正することが大切です。
飼育ケージ
一般的に求められる条件は、飼育個体に対して十分な広さを持つこと、脱走できないこと、温度や湿度の管理がしやすいこと、給餌や清掃といったメンテナンスがしやすいこと、観察がしやすいことなどです。
樹上棲の種には底面積よりも高さを重視すべきですし、リクガメ類のように行動範囲が二次元的な種には底面積が重要になります。水を張って飼育する必要のある水棲カメ類には観賞魚用の水槽が用いられることが多いと思いますが、陸上部分を設ける必要があることと、水深を深くとることによってカメの行動空間を広くできること、水量の増加による水質悪化の鈍化などのメリットから、なるべく深い水槽を選択すべきです。
小型種であっても、広いスペースを与えないと精神的に安定しない種や個体が存在します。個体が小さいからといって短絡的に小さなケージで飼育することは避けるべきでしょう。
また、一部の種を除いては個体間の干渉が激しいことが多く、一個体一ケージが基本となります。
飼育ケージ内の調度
樹上棲種には止まり木を、隠れる性質がある種にはシェルターを、といった種ごとの要求に合わせたものを用意します。自然を模して、美しくレイアウトすることは飼育の大きな楽しみの一つとなりますが、メンテナンス性には注意を払いましょう。
床材の選択には頭を悩ませることが多いのですが、歩きやすいこと、ほこりが出にくいこと、汚れが目立ち清掃や交換がしやすいことなどを基準に選びます。また、多湿を好む種には保湿性が高いもの、乾燥した環境に生息する種には、濡れてもすぐに乾くものを選択します。
温度管理
爬虫類は外温動物ですから、それぞれの種の要求に沿った温度管理を行う必要があります。温度により代謝機能が変動し、成長、内分泌、消化などに大きな影響を与えます。必ずしも熱帯産の種が高い温度を好むという訳ではなく、飼育種ごとの至適温度帯を把握して飼育環境の温度を設定します。わが国の夏の気温は、種によっては致命的な場合があり、低温を好む種の飼育にあたっては、エアコンによる温度管理が必要な場合もあります。
重要なのは飼育ケージ内に温度勾配を設けて、飼育個体がその時点で最も快適な温度の場所に移動できるようにすることです。ホットスポットと呼ばれる高温の場所をケージの一方に設置し、もう一方は低温になるように、このためにも飼育ケージにはゆとりのあるサイズが要求されます。
冬季の暖房に対しては、様々な保温器具が販売されていますが、大切なことは保温電球のような空気を暖めて飼育環境そのものの温度を上昇させるタイプの器具と、パネルヒーターのように動物自体を暖める器具を必ず併用することです。温帯に分布する種に対して冬眠を試みたり、無加温で越冬させようとする飼育者が見られますが、前者については相当の飼育スキルが必要なこと、後者については動物の生命を危険にさらす可能性が高いことから、基本的には避けるべきです。
温度は目に見えません、最高最低温度計の設置は爬虫類の飼育にあたって必須の装備です。
湿度管理
熱帯雨林に生息し高い湿度を好むものから、砂漠に住み乾燥した環境に適応しているものまでさまざまな種がいます。いずれも通気性を十分に確保することが大切で、たとえ高湿度を要求する種であっても蒸れるような環境では体調を崩します。
また、冬季の極端に湿度が低下する季節には、暖房することによる乾燥とあいまって砂漠棲の種であってもしばしば脱水を起こすため、霧を吹くなどして最低限の湿度の確保に努めます。
照明
例外はあるものの、多くのヤモリのような夜行性の種や、多くのヘビ類は照明を必要としませんが、多くのカメ類のような昼行性の種には必ず照明を設置し、昼間の時間帯に点灯するようにします。
爬虫類の飼育においては、古くから特にカルシウム代謝に大きな影響を持つ紫外線の照射に関心が高く、現在ではこの点を重視した照明器具が多く開発、販売されているので、こうした製品を利用します。ただし、紫外線は強ければよいといった性格のものではなく、種ごとの紫外線要求量に見合ったものを選択します。
直射日光による日光浴は、大いに奨励されますが、通気性の確保及び動物が避難できる日陰の部分を用意することと、日光浴時の気温に十分な配慮をしないと熱死させてしまうことがあります。
また、昼行性の種であってもむやみに明るい環境は好まない種も存在します。このような種に対してはシェルターを設けたり、飼育ケージに対して小型の照明器具を使用するといった配慮が必要となります。
湿度管理
熱帯雨林に生息し高い湿度を好むものから、砂漠に住み乾燥した環境に適応しているものまでさまざまな種がいます。いずれも通気性を十分に確保することが大切で、たとえ高湿度を要求する種であっても蒸れるような環境では体調を崩します。
また、冬季の極端に湿度が低下する季節には、暖房することによる乾燥とあいまって砂漠棲の種であってもしばしば脱水を起こすため、霧を吹くなどして最低限の湿度の確保に努めます。
食餌と水
人工飼料が非常に発達しており、これだけで終生飼育が可能な水棲ガメ類以外の種においては、飼育している種に合ったエサを与えなければなりません。
肉食の種には、エサ用に販売されている昆虫類やマウス、魚、貝類、脂肪分の少ない肉などをそれぞれの種の食性に合わせて与えます。特にコオロギやミルワームといった昆虫類はカルシウム・ リン酸比が悪いので必ずカルシウムの粉末をまぶして与えるようにします。これに加えてビタミン、ミネラルなどの粉末も定期的に加えます。マウスは完全栄養であると考えられることが多いのですが、冷凍されたものはビタミンが破壊されていることを考慮し、やはり定期的なビタミンの添加が推奨されます。
草食種には、市販の野菜、果実、野草などを与えます。ここでもカルシウムとビタミンの添加は必須となります。
雑食で、何でも食べるから飼育しやすいという表現をされる種がいますが、これは逆に様々なものをバランスよく与える必要があるということで、必ずしも飼育しやすいわけではありません。入手しやすい食餌に偏ることのないように注意が必要です。
飲用の水は必ず用意します。トカゲ類には止水を水と認識しない種がおり、霧を吹いたり、ドリップ式の容器を用意する必要もあるでしょう。乾燥した地域に生息するリクガメ類には、水を飲もうとしない個体が見受けられます。このような場合は、無理に飲ませようとするよりは、食餌にレタスやキュウリなどの水分量の多いものを混ぜて与えるとよいでしょう。ヘビ類には必ず全身を浸すことのできる水容器を設置します。
飼育について、より詳細な情報をお求めの方
より詳細な情報をご覧になりたい方は、下記のPDFファイルをご参照下さい。
※上記の記載は、下記PDFファイルの抜粋になります。
環境省 『ペット動物販売業者用説明マニュアル』「動物の特性と飼養方法」 より
|

哺乳類・ 鳥類・ 爬虫類 |
pdfファイルをご覧になるには、adobeリーダーが必要です。
adobeリーダーのダウンロードはこちらから→ |
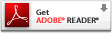 |
|



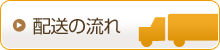
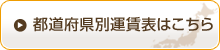
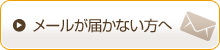

![TEL 0266-44-3952([平日] 15:00~19:30 [土曜日及び日祭日] 13:00~20:00 定休日無し ※臨時休業有り) FAX 0265-79-7977](/user_data/packages/kittou/images/base/banner_mail.gif)
